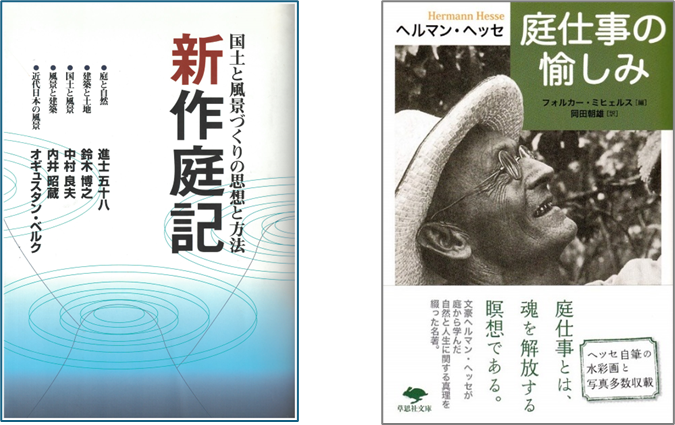2024年8月の盆休み、退屈していたことから、富山の自宅庭が荒れ放題になっていたのを何とかせねばと考え、手元にあった庭造りの本に目を通す。
ヘルマン・ヘッセの「庭仕事の愉しみ」(1996.6 草思社)は何度も目を通していたので後にして、富山の庭は「枯山水」が似合うように思ったので、重森三玲著「灯籠と蹲」を参考にして石灯籠を入れたことから、先ずは、この「枯山水」について改めて読んでみる。しかし、本格的枯山水のコストを考えると不可能である。
結果として、Blogの表題の著書を手にすると、すでに熟読していたらしく何カ所にも折り込みや傍線がつけてあった。その上、本書は内田昭蔵先生からの贈呈で、手紙も入っていた。
改めて本書を読むと、連著書の第5章 オギュスタン・ベルク氏発言が気になった。1942年生まれで、当時、フランス国立社会科学高等研究院教授、1984~86年、日仏会館フランス学長で、「日本の風景・西欧の景観」(講談社現代新書)や「風土の日本」(ちくま学芸文庫)の著書があった。以下に彼の著述(翻訳:篠田勝英)を抜粋引用する。
・私は日本に興味を持ち、この国のことを学び始めて30余年。日本語の「主体」「主観」「主語」「主題」の四語はフランス語や英語では一つの単語である。日本語の読み方を学ぶヨーロッパ人が直面する問題は「主語」の明示されないのが日本文である。そういう日本文においては、いかなる語も主語の代わりをしない。語っている人物の状況と身分に応じて変化するからだ。
・明治期に、日本の地理学者がドイツ語のLandschaft、英語のLandscape、フランス語のPaysageを「景観」と訳した。この時期、日本の画家達が「山水画」を「風景画」として語り始めたのは、主体の関係の変化であった。とりわけ「景観」という語は、主体から客体に向けられた視線の存在を前提とする。山水(風景)から「景観」に移行することは、文字通りの転倒が含まれている。「山水」の場合、重要なのはモチーフ(山ないし水)であり、「景観」の場合、視線「観」、すなわち主体の存在である。そして、その主体にとってモチーフ(「景」)が客体となるのである。
一方には「景観」の研究を客観的な科学にしようという近代日本の地理学者の意図があり、他方には、後述する黄枝の句*によって示したような風景の伝統があった。実のところ、両者は両立しがたいものであった。その当時、日本人全員がこの両立不能の「体験」をしたのだった。
*「風鈴の ちひさき音の 下にゐる」黄枝の句
視覚以外の感覚(肌に感じる爽やかな風を喚起する音)によって、さらには体感(生活様式)、雰囲気は主体ではない「ゐる」の主語は存在しない。主語の不在が場面を活性化している。この様な風景が日本に存在するからで、日本語の表現がこれを可能にするから、このような句が生まれる。
逆に、日本の地理学者が「景観」と訳した客体としては、ドイツのLandschaftほど深い根を持っていなかったことは明白である。
○作庭記とは、風情を巡らして空間と景観をつくる思想と方法である。
○主体と客体について、私が考察するところ(主体「観」の対称にあるのは客体「景」である筈が、主語を明示しないことによって景観のあり方を不明、曖昧、いいかげんにしたが、それを良しとするのが日本文化。)
人間と(時間)空間を対比するように
地理学と自然(地球の自然)
社会学と風土(固有の風土)
作家と風情(人格を求める)
画家と風景(美しい風景を描く)
建築家と景観(実景をつくる、設計者)
物理学と環境(環境を破壊する)
戦後の日本経済がバブル期にあった1990年代、建築自由の日本社会にあって、ヨーロッパ等の先進諸国に比し、無秩序な乱開発(屋外広告など)として景観の価値が問われ、2004年6月、国土交通省では景観緑三法を公布する。
1999年11月には黒川紀章や藤沢和氏によって日本景観学会が創立された。日本の都市景観に対する取り組みが全く進まないのは、都市の主体者が不在であること以上に、その「ウラ」にもっと深い日本文化の特性があり、主体(責任者)を曖昧にしてきた故か?本書のオギュスタン・ベルク氏の学説を日本景観学会でも再検討する価値がありそうだ。足立美術館の庭、東京の自宅の庭、八ヶ岳山荘の庭、そして富山の留守宅の庭造りにも主体者不在を認識させられた上、何故かヘルマン・ヘッセの「庭仕事の愉しみ」を再読せずには居られなかった。