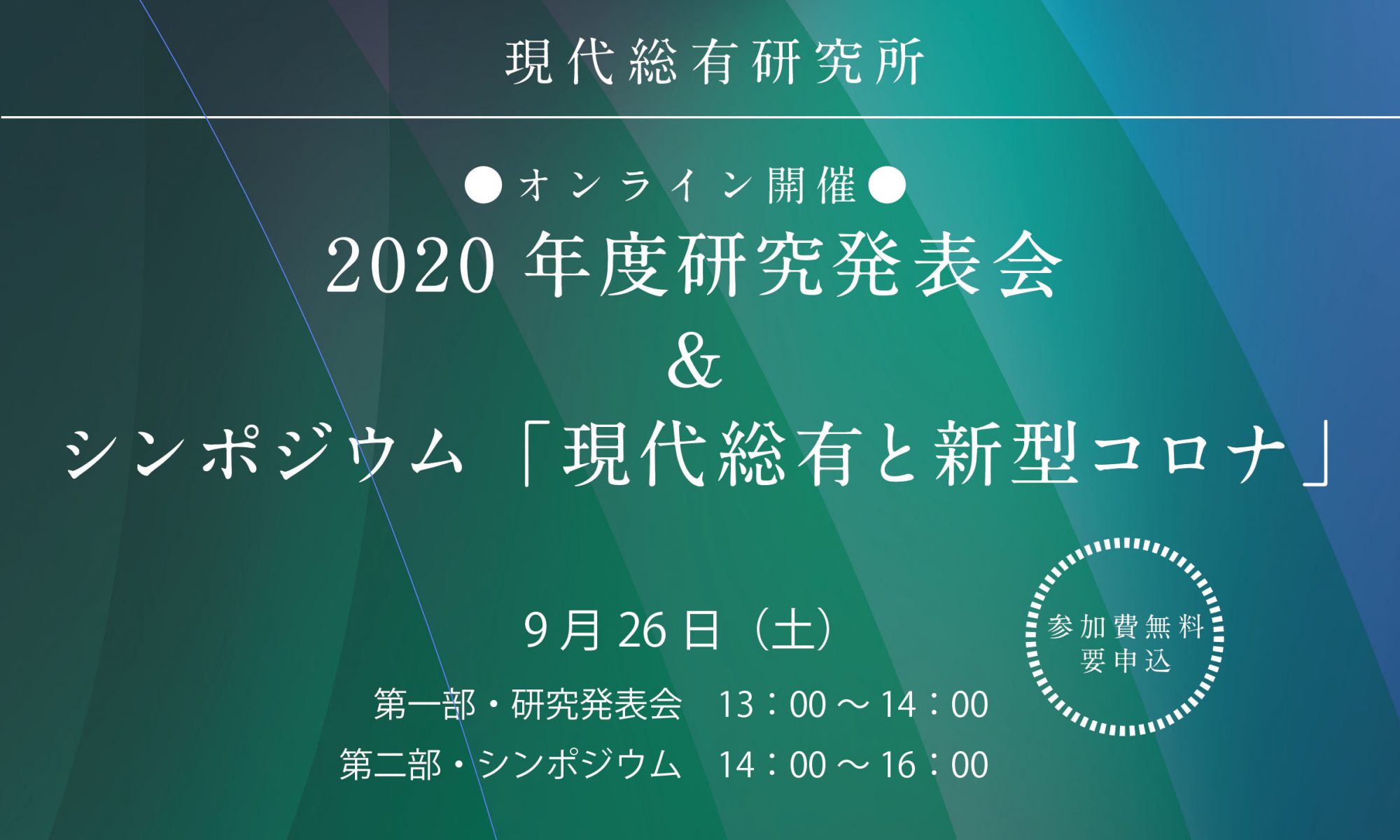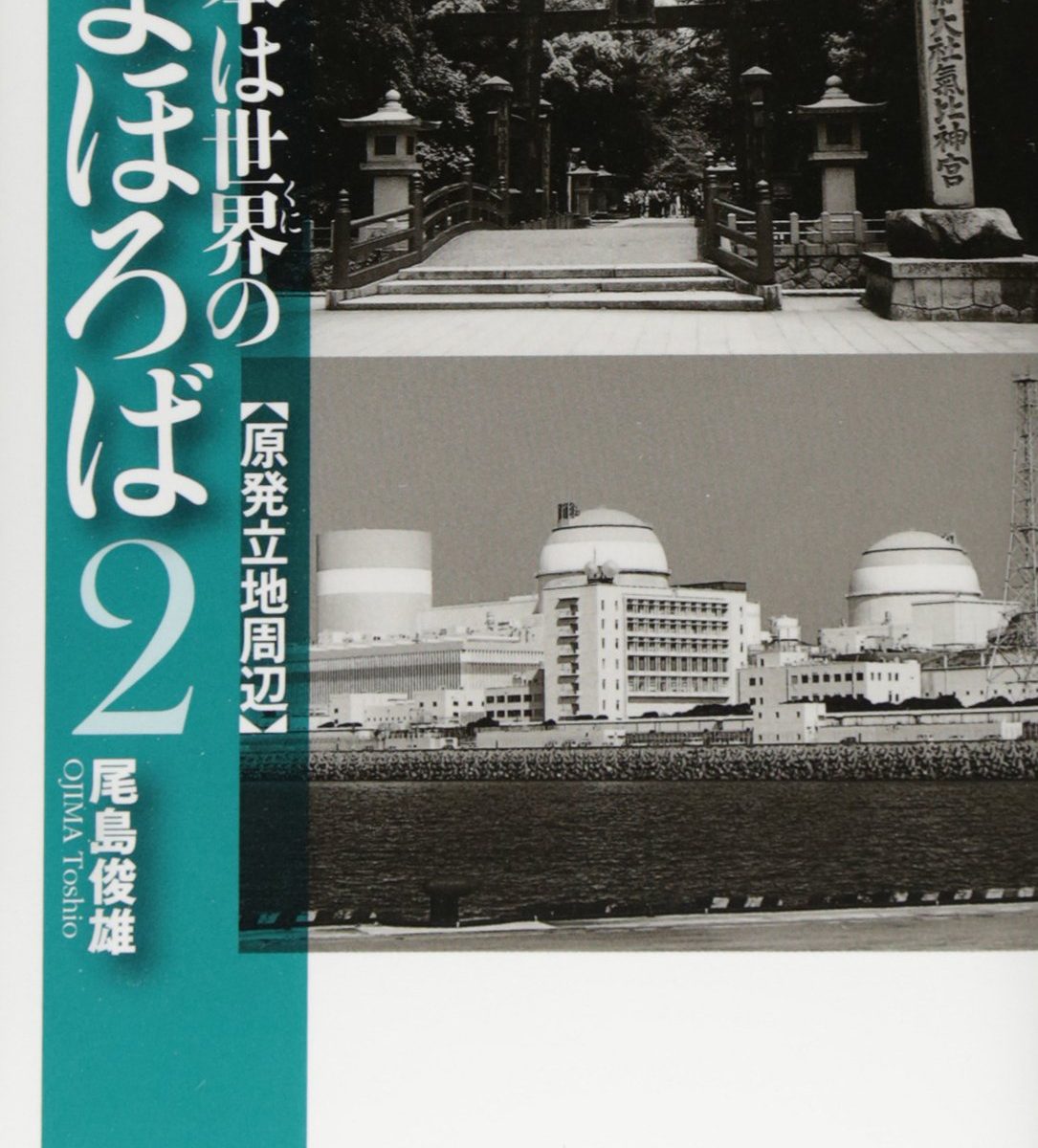私は昭和12年、富山県富山市に生まれ、83歳になります。今日の各先生方の話題は、私自身の人生・体験と重なり、誠に感慨深くお聞きしていました。
昭和12年は、北京郊外の盧溝橋で日中戦争が勃発した年で、この戦争がそのまま太平洋戦争に続いて、昭和20年8月15日の終戦を迎えます。
しかしその直前の8月1日に、私が生れ育った富山市が、米軍のB29の空襲で全滅全焼、10万人の市人口の内2000人もの人が亡くなりました。私の向かいの一家、8人全員が防空壕で亡くなりました。私の自宅も土蔵も、小学校も全て全焼してしまい、黒部市に2年間疎開しました。ともかく食べるものもない時期でしたが、子供心に明るかった。
2年間の疎開生活の後、富山市に戻りました。小学校はまさに青空学級で、食べるものもない貧しいバラック家で、その頃から、家を建てたい、学校をつくりたいと、建築家を志して、早稲田大学に入学したのは1955年でした。
1950年の朝鮮戦争勃発で、日本でも防衛大学が創設されたり、自衛隊をつくるとか、アメリカから軍需物資が流れ込んで、朝鮮戦争は日本に大きな特需をもたらした。建築や造船・鉄鋼などの重厚長大産業が、日本の復興のため大躍進する時代にあって、大学の先生方で、構造力学とか材料、私が学んだ設備分野に、日本の陸海空軍の技術将校が、先生として、また学生として仲間に入ってきた。日本の建築技術は飛躍的に発展した時代です。
一年生の時に、東京タワーをつくられた内藤多仲先生の構造力学で、東京タワーは、パリのエッフェル塔のように鋳鉄ではなくて、戦車のくず鉄を焼き直して造ったことで、エッフェル塔の2分の1程の重さでありながら、エッフェル塔より高くて、地震に耐える設計をしたという話を聞きました。
1964年の東京オリンピック時には新幹線ができ、又、丹下健三さんが設計した代々木のオリンピックプール、その設備を私の恩師・井上宇市先生が担当した。井上先生は東大の造船学科を出た海軍中尉で、潜水艦の設計をしていたという先生の指導を受けてオリンピックのプールを手伝いました。そのお礼で1965年にアメリカに一緒に行かせて頂いた。
はじめてニューヨークに行き、日本との格差の大きさに驚きました。井上先生のアメリカ訪問は、東京駅を超高層にするため(当時31mの高さ制限)の調査が目的であった。
当時、ニューヨークでは世界博を開催しており、会場の外は暑くて、パビリオンの中は涼しい、その温度差を体験したことから、地域冷房の必要性を感じたこと。バウハウスの校長であったグロピウスの設計したパンナムビルがセントラルステーションの裏に造られたことで、超高層建築がパークアベニューの風の道を阻害していることを体感したことが、東京駅が八重洲通りと行幸通りの風の道づくりの阻害になる研究に結びつくわけです。東京駅は超高層にならなかったけれども、その時の調査で早稲田大学の55号館や霞が関ビルの設計に役立った。
丁度その頃、私の先生や大成建設の方々が、ソウル大学の建築の先生方と協力して、韓国で初めての大韓生命ビルの超高層を設計していた。当時の韓国は、技術や産業基盤で日本より4~5年遅れていたような気がしますが、兎も角にも一緒に仕事をされていた。
日本も韓国も、ある意味では技術的に頑張った時代。私たち大学院の学生が、オリンピックプールの設計や超高層の設計をしたり、さらには万博の設計をすることになるのも、先輩がほとんど戦争でいなくなった時代です。修士・博士の大学院生は数も少ない上に、授業もないわけで、アメリカやヨーロッパの文献や原書を読む研究だけが大学院生の日課でした。英語やフランス語・ドイツ語やロシア語の文献を私たちが訳す。それがバイトになり、大学院のゼミや文献研究の仕事でした。
30代で大阪万博の会場設計をやることになり、300haの土地に6000万人が集まる会場で3万冷凍トンの地域冷房の基本設計をしました。
アメリカのパビリオンが1500冷凍トン、ソ連が2000冷凍トン、日本が2000冷凍トン、あるいは三井とか三菱のパビリオンが700冷凍トンくらいの冷房負荷の建物を造ったのですが、それに対して、中国300、韓国200、インド250、インドネシア150で、日本を除くアジアの全てを集めても1000冷凍トン。要するに、日本館一館にも及ばないくらいが当時の万博のアジアパビリオンのスケールであり、国力でした。
1970年代に大きな変革がありました。佐藤栄作が総理で、田中角栄が通産大臣の1972年の沖縄返還後、沖縄振興のために海洋博を開催するに当たって、那覇ではなくて本部半島という北の方に万博会場を造ることで、そこまでの交通や電力・水などの供給とか、島全体の返還に伴うインフラストラクチャーを提案することになり、高山英華先生の下で、私がお手伝いしました。特に沖縄海洋博の事務総長は、沖縄出身で、早稲田大学の大浜信泉総長が担当されたこともあり、高山先生や大浜先生、さらには中曽根通産大臣の直轄下に、沖縄全体のインフラ設計を手伝わせて頂きました。当時、沖縄には東電や九電に相当する電力会社がなかったので、九州電力や東京電力の支社でなく沖縄電力をつくるべきだと生意気にも主張したりしながら、沖縄海洋博会場でもサンゴ礁の破壊を防ぐ赤水対策等、新しい会場インフラを造るためにはエコロジーケアの大切さを、その設計を通して実感した訳です。当時はローマクラブの「成長の限界」が話題であり、大学の研究テーマでもあった。
沖縄海洋博後の1978年に日中平和条約が結ばれ、鄧小平が日本にやってきました。彼は新幹線を体験して、青少年の友好交流とか理工系教授の交換などを提案しました。私は、日本の都市開発もさることながらエコロジーが大切だと痛感しており、中国は自立更生で自然生態都市として成果を収めていましたので、その実態を勉強したいと、交換教授に申し出ましたら、早速、招待状が届き、1979年に中国に行くことになりました。
9月に北京の中国科学院に行きまして、北京飯店に分室があったのですが、そこで中国全体の様子を学び、その後、彼等に気に入られたみたいで、中国の先生方との交流を希望するなら何処がいいかと仰ったので、私は西湖のある杭州を希望したところ、中国の重点大学で、中国科学院直轄の大学である浙江大学に、半年間、中国全土から優秀な学者が集められて、彼等と合宿して交流が始まりました。浙江大学を拠点として、中国の各重点大学に表敬訪問しながら60回も講演や講義をしました。
帰国した後も日中の交流の橋渡しをしてきました。そういった成果のためか、1986年に建築学会百周年の会長になる芦原義信先生が突然自宅に来られて、開かれた学会をつくるためには、どうしてもアジア、特に中国を中心に交流してほしいと頼まれたので、1986年以降、日本建築学会を中心にアジア各国との交流会を開きました。しかし、1989年に天安門事件があり、鄧小平から江沢民体制になり、反日教育が激しくなる中で、私自身が親しくしていた先生方が表に出て来られなくなったこともあり、交流が少なくなりました。
1990年以降は、1995年の阪神大震災や2011年の東日本大震災等、国内のことで忙殺されて今日に至っています。唯、日本国内のみならず、アジアからの留学生やその弟子達を中心に、毎年1回、アジア都市環境学の国際交流を続けています。