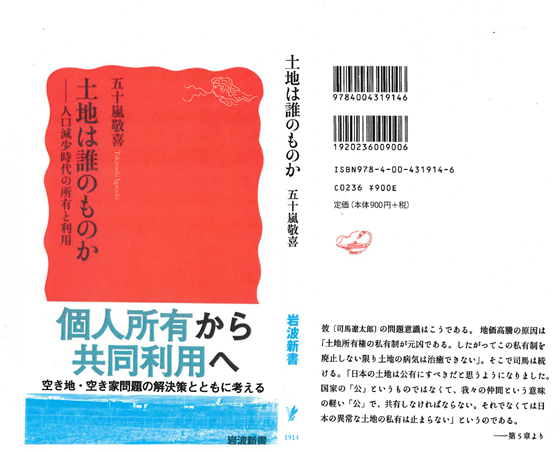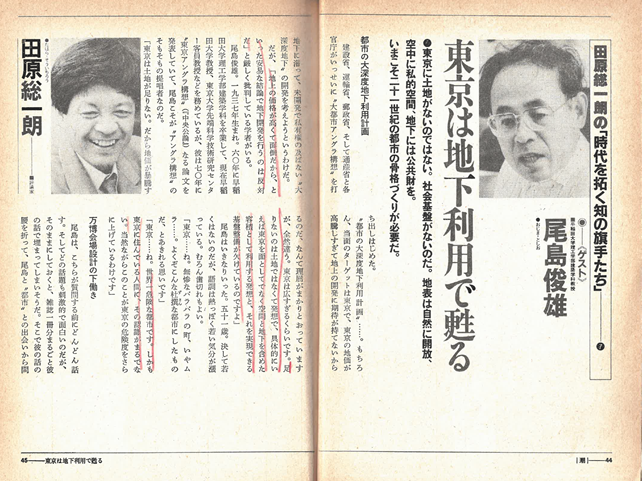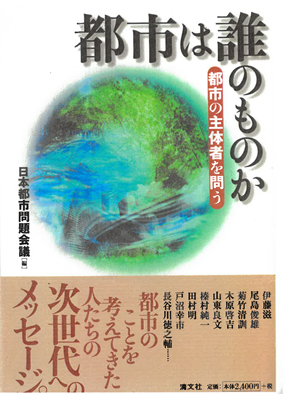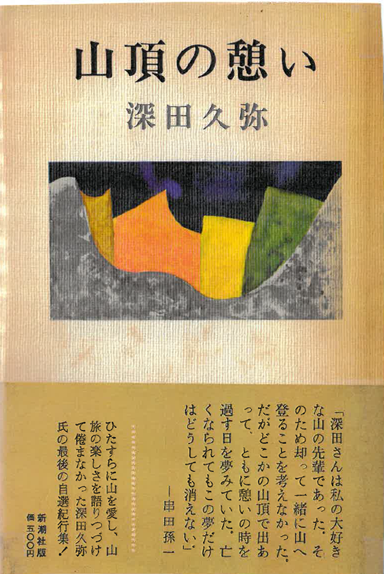2022年2月1日(火)、池袋のホテルメトロポリタン3階の大会議室で定期講習の考査を受けた。建築事務所に在籍する建築士は3年に一度、定期講習を受けた後に簡単な修了考査を受ける義務(受けないと懲戒処分を受ける)のある第5回目の講習と修了考査である。
2005年の姉歯事件(構造計算書偽造問題)をきっかけに、性善説から性悪説に変革して、この新建築士制度がスタートした。同時に、建築事務所の開設者は、管理建築士資格者を置く必要性や保険への加入協力義務制度も発足した。その結果、私自身も立場上、新制度発足と同時に、2009年11月に第1回の一級建築士講習、2010年6月に管理建築士講習、2012年6月に第2回、2015年7月に第3回、2018年11月に第4回を受講したが、80歳を越えたことから、5回目は長時間の講習や修了考査を受ける苦痛から解放されようと考えていた。
しかし、2020年からのコロナ禍で、この制度上の講習はweb上のビデオ講習でOK。しかし修了考査は従来通りという案内が来た。修了考査を受けるかどうかは別として、これまで定期講習を受けた体験と、建築士たる者の倫理観から、webによるビデオ講習は受講しておこうと考えた。
結果は、なかなかに価値ある情報提供で、最近の空き家問題、糸魚川大火や熊本地震、洪水被害からの法改正や新告示等、建築士たる者は3年に一回は社会状況を知る必要な制度に思われた。開業医や弁護士と共に、建築家は三大自由業として、その分野の職能独占権を与えられている以上、権利と共に義務も発生している。それにしても3年に一度の定期講習と修了考査は本当に面倒で、博士学位と同様、一級建築士の資格は「足の裏に張り付いたお米」の例え通り、取得してもすぐに仕事に恵まれるわけではない。その上、大きな建物は、別に一級構造建築士や設備士の関与が義務付けられたから、免許の守備範囲も限定された。かくして、この制度のみならず、久しく建築基準法のあり方そのものが問われており、これをイギリスのように地方の安全条例として、別途、建築基本法を制定すべきとの声もある。
昭和38年7月10日付、河野一郎建設大臣名での一級建築士免許は紛失したため、いま手元にあるのは平成15年7月10日(登録40525号の林寛子国土交通大臣名)の再交付免許証である。この免許証は、昭和35年4月、早大理工建築学科を卒業して、2年間の実務経験(大学院修士課程在学中)を経た上で、学科目と設計の実技試験に合格(合格率20%(当時))した証書である。この当時の一級建築士免許は、博士課程時代の構造計算や設計図書のバイトには有効であった。
しかし昭和40年から大学の教職についたので、一級建築士の資格免許証を使うことはなくなっていた。昭和57年(1982)から平成28年(2016)迄の34年間、練馬区の建築審査会委員(委員は5名、建築基準法に関して特定行政庁が法の例外的取り扱いに当たって同意を与える権限をもつ)を務めたことで、赤本と称する分厚い建築基準法を毎月一回は見る機会があった。そのため、最新の法律や告示が改正されたことを知ることができた。
1997年に日本建築学会の会長に就任した頃、1995年の阪神・淡路大震災から構造系の法改正や、1997年の京都議定書・COP3の地球温暖化対策に当たって、文部科学省所管の建築学会が中心になって各種の基準作成に当たった。建設省所管の建築士会や建築家協会、建築事務所協会との交流や土木学会との役割分担等、建設業界のあるべき姿を模索すると共に、学会として倫理綱領を定める必要を痛感した。
また、2005年には日本学術会議から「大都市における地震災害時の安全の確保について」を小泉純一郎首相に勧告、重く受け止めるとの回答。その成果もあって、2008年の新建築士制度の発足となって、3年に1回の定期講習と修了考査を受けざるを得なくなったことを改めて考えてみた。37万人もの誇り高き一級建築士と75万人もの二級建築士に加えて、7万社以上の一級建築士事務所開設者とその管理者は、3年に1回と義務付けたこの定期講習と修了考査は、内容次第で国土強靱化やカーボンニュートラルの国家目標の達成に大きな戦力になると考えた。コロナ禍の自宅でくつろぎながら、webで受講した内容は、満席の大教室で聞かされる講習とは違って新鮮であったこともある。 2月1日に講習修了考査を受けてすぐ、このBlogを書いたが、それから3月25日付「建築士定期講習修了書」を受領するまで、考査に合格したかどうか、40問中、何問間違ったかなど気になっていた。自動車の免許証同様、高齢者は免許を返却すべきにも思えてきた。この制度も再考すべきかと思ったのは、免許書換え交付の手続きをせんとしたところ、申請書類のExcelテンプレートの生年月日が昭和16年からしか記入できず、困ってしまったので。