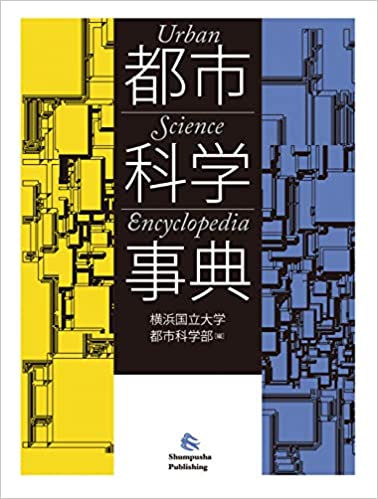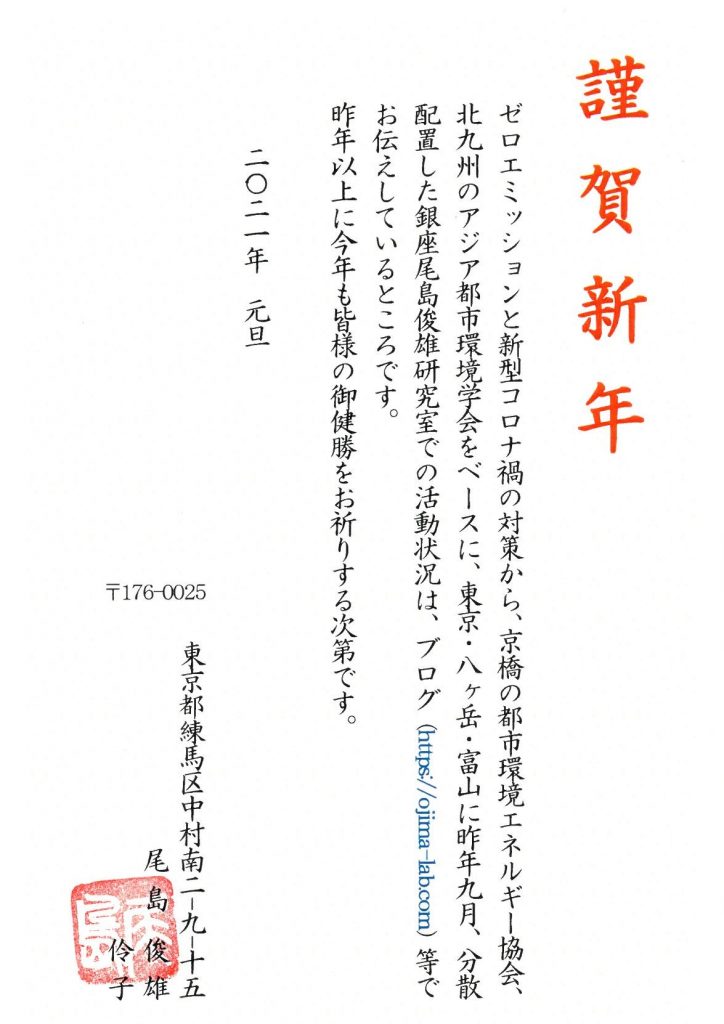縄文社会研究会の雛元氏から松浦先生に土木の語源を問うメールがあった。
土木と同じ建築の語源についても諸説あり、いつかこれを明確にしておくことが必要と考えていた。2021年の私の見解は、“Civil Engineering”を初めて日本語に訳した人は誰かわからないが「土木工学」と訳し、“Architecture”を日本語に訳した人も誰かわからないが「建築」と訳した。唯、その訳語が正しかったかどうかわからないが、明治の初期にこの訳語を普及させた人は、建築については、間違いなく東大の初代建築史教授であった伊東忠太であり、土木についてもよくわからないが、土木学会の式典で、紀元前2世紀頃に記された『淮南子』に基づき命名されたと北大総長の丹保憲仁教授が話され、普及したようである。又、早大建築学科を卒業して、東大土木工学科の教授になった内藤廣君も「土木」と「建築」の語源に関心をもって調べているようだ。
東大の建築学科は、初期は造家学科と称し、日本建築学会も創設期は造家学会であった。土木学会は工学会からではなかったか。
言葉は時代の生活・文化と共に変わり、何故そうなったかについてはよく分からないのが普通で、今日使っている中国語の建築や土木の用語も、日本語の翻訳を活用したものと考えられる。
いずれにしろ、明治維新、日本が欧米文化の輸入に熱心であった時代の訳語で、いつかこの言葉が定着し、更には日本独自の建築や土木の文化が生まれていると考えてよかろう。ちなみに、江戸時代の建築に相当する言葉は「作事」であり、土木は「普請」と称していたようだ。
以上、私の勝手なBlogに記したいと考えたが、念のため、用語に詳しい松浦茂樹先生と高橋信之先生に教えてほしいとメールした。数日して数十頁の調査資料が送られてきた。余りに多様な説明があったので略記して、両先生の了解を得られれば、私自身のBlogに引用させて頂くことにした。なお、手元にあった伊東忠太の書物を読んで、言葉の定義は時代と共に変わっていくことを実感すると共に、私の専門とする「都市環境」という言葉も、この30年間でずいぶん変わってきた。
①伊東忠太著「日本建築の美」(昭和19年6月、築地書店)
②伊東忠太著「木片集」(昭和3年5月、萬里閣書房)
③岸田日出刀著「建築学者 伊東忠太」(昭和20年6月、乾元社)
④読売新聞社編「建築巨人 伊東忠太」(平成5年7月、読売新聞社)
日頃何気なく使っている用語が定着するためには、大変な歴史やその用語に対する思い入れのある人々の多いこともインターネットや両先生からの資料を読んで痛感した次第である。
「土木」の用語由来
・1869年(明治2年)、民部官土木司が設置され、職制にはじめて「土木」が登場し、明治10年内務省土木局が設置され長く続いた。
・一方、明治元年、会計官が設立されるが、その直前の4月15日の記事に「開墾土木、工事」の用語が記載され、設立後の8月22日の記事に、天竜川堤防修築工事を浜松藩に委任するに当たって、「土木ノ事務タル本官ノ専任に属ス」と土木の用語がある。
・明治2年8月11日、大蔵省から営繕司の事務が民部省土木司に転属。土木事務・公共建築事務のすべてを担当する。
・明治4年7月14日の廃藩置県で民部省廃止につき、土木司は工部省土木寮が所轄するも、土木寮は大蔵省・内務省に移り、明治7年内務省土木寮の営繕事務が工部省に移される。内務省土木寮所轄の建築局が工部省製作料の所管になる。明治10年、寮は局となり、内務省土木寮は土木局となり、1931年(昭和6年)まで55年間続く。
・明治6年刊行の「英和字彙」に”Civil Engineering”が登場し、「土木方」と記されている。
・明治元年刊行の「軍事小典」に「土公兵」なる用語は、Military Engineerを訳したもの。
(以上、松浦氏調査資料より)
「土木」用語の由来
・土木関係者は、2002年5月の土木学会の式典で、丹保憲仁前会長の記念講演で『土木の語源は、紀元前2世紀頃の中国古典「淮南子」に(聖人乃作 為之築土構木 以為室屋上棟下宇 ・・・)』この築土構木からとの説。しかし大正5年頃の土木学会誌で土木ノ改名論に関する激論あるも、築土構木の出典は伝聞としている。しかし、「土木」の二字の歴史は、「淮南子」より3世紀以上前に、中国の「国語」等に2回も登場し、日本でも鎌倉時代の「源平盛衰記」に東大寺建立を叙述したところで「土木(ともく)ノ造録」がある。
「建築」の用語由来
・堀達之助(1823~1894)等編「英和對譯袖珍辞書」(文久2年(1862年)、洋書取調所、出版地:江戸)
Architect 建築術ノ学者
Architecture 建築学
明治4年11月「袖珍英和節用集 全」に同じ訳
・明治2年(1869)薩摩辞書、上海にて印刷刊行
・明治6年(1873)「東京新製活版所蔵版和譯英辞書」
Architect 建築学者
Architecture 建築術
・明治6年(1873)「工学寮・学課並諸規則」
・専門科ヲ分チテ土木・機械・造家・電信・化学・冶金・鉱山ノ七科トシ六ヶ年ヲ以テ卒業ノ期トス。
・明治18年(1885)工部大学校 学課並諸規則
学課:Build、Construct等に建築
Architecture 造家
・明治19年(1886)造家学会発足、発行雑誌名「建築雑誌」
正員は建築学を専修したる者
・明治27年(1894)伊東忠太「我造家学会の改名を望む」(明治30年3月発行の建築雑誌)
・明治30年(1897)造家学会を建築学会に改名
・明治31年(1898)帝国大学工科大学造家学科を建築学科と改名
(以上、高橋氏調査資料より)
尾島の蛇足ですが、
20世紀後半に輝いた丹下健三や菊竹清訓に代表される日本の建築家や、世界に誇る長大橋や海底トンネルを建設した土木技術者の名声や成果を礎に、建築と土木を合わせた建設産業が花形であった。しかしその時代こそ、日本の失われた30年間であったようで、結果として、日本は世界のDX(Digital Transformation)に乗り遅れた。
果たして、理工学部の建築学科や土木工学科は、建築学部や社会工学科へと発展・解消する方向に名称を変え始めた。建設業界も”Construction”から”Production”へと、アナログからデジタル技術へ転換、”Architecture”や”Civil”の用語も、BIMやCIM時代にあって、その意味するところが、最近よく使っている人々の声から、建築や土木の専門家ではなく、情報分野に属している人々のようである。
建設産業界に際立つ高齢化や人手不足、生産効率の低下は、建築や土木の技術や文化に執着した私の世代が世界の潮流に乗り遅れているためであろう。コロナ禍のステーホームでは反省ばかりである。