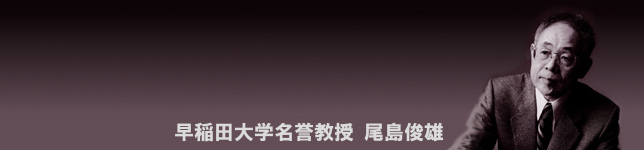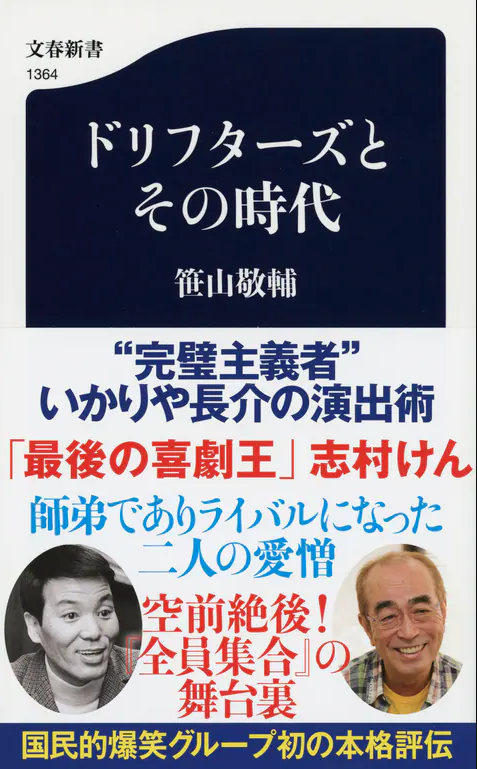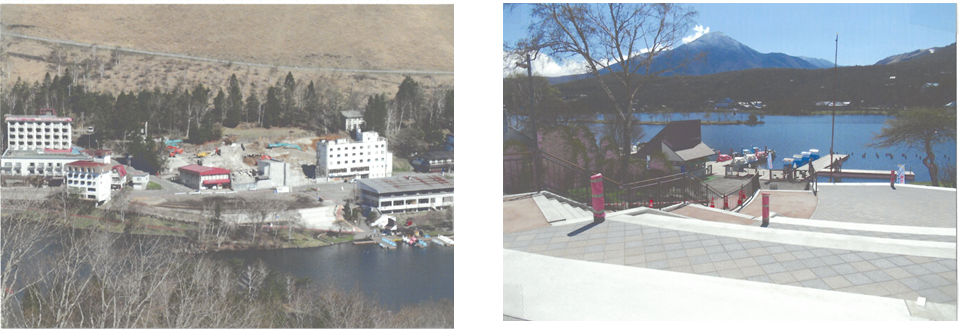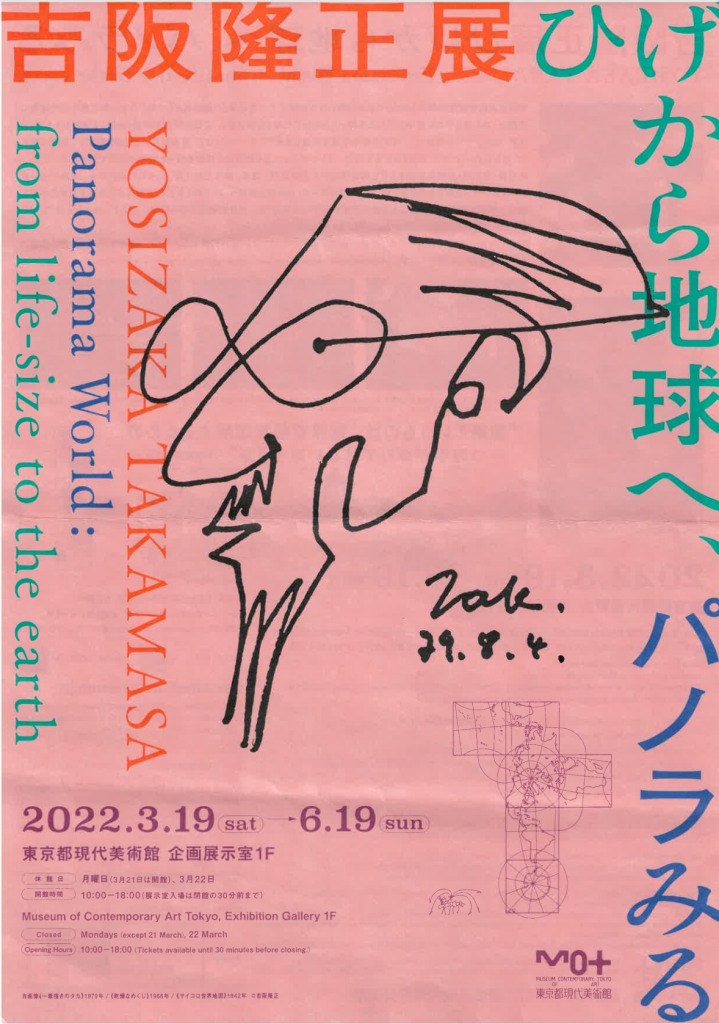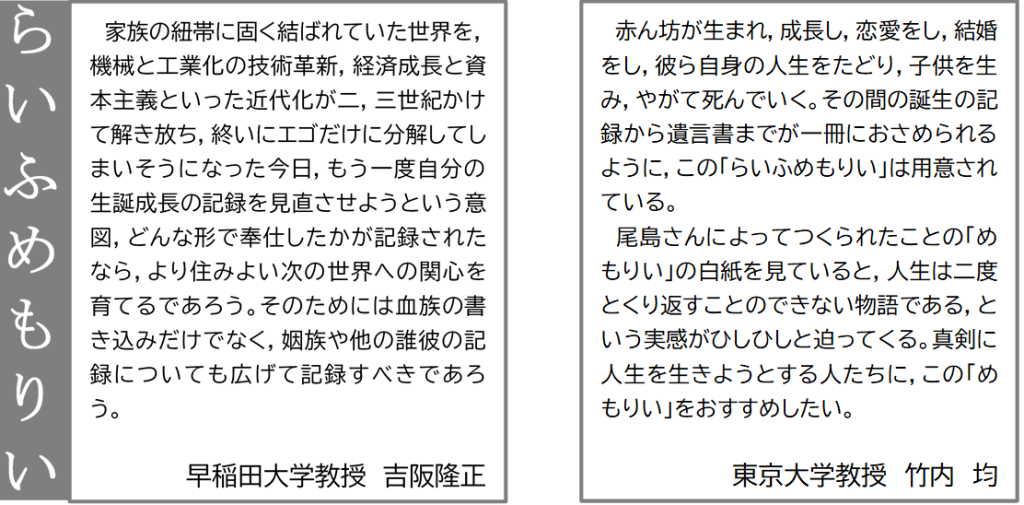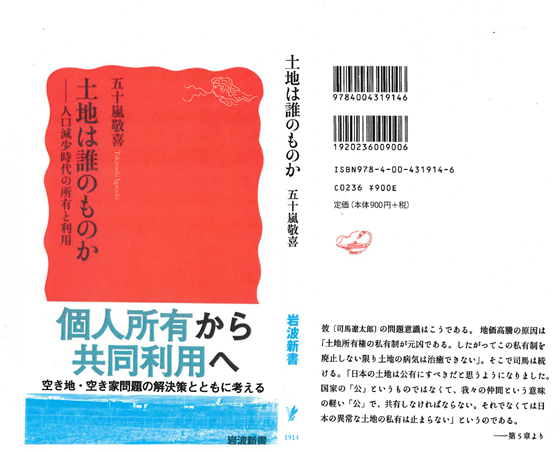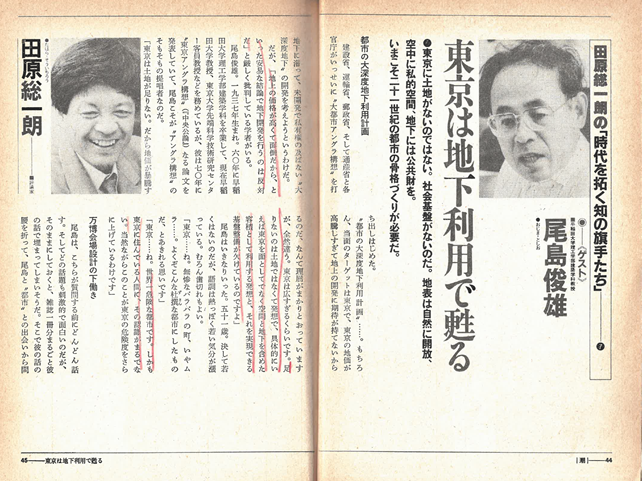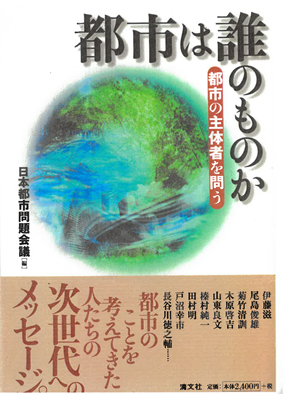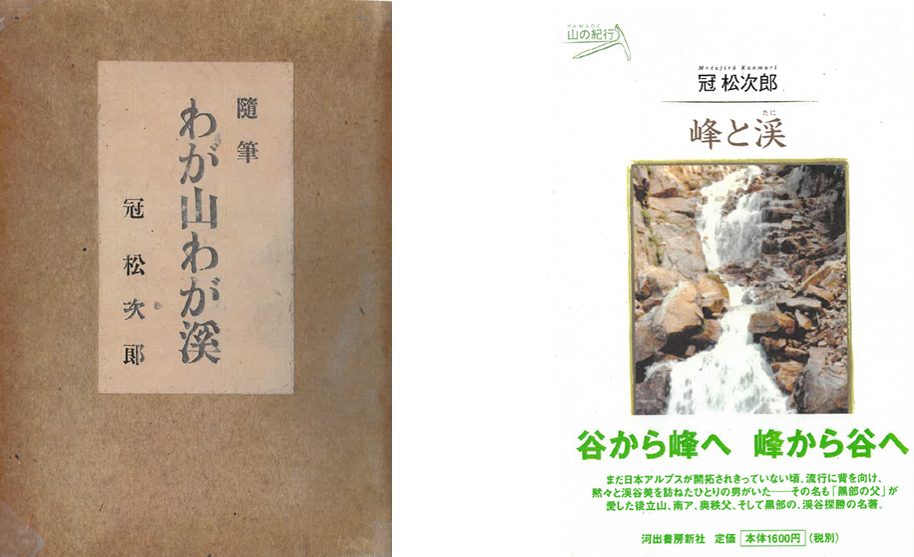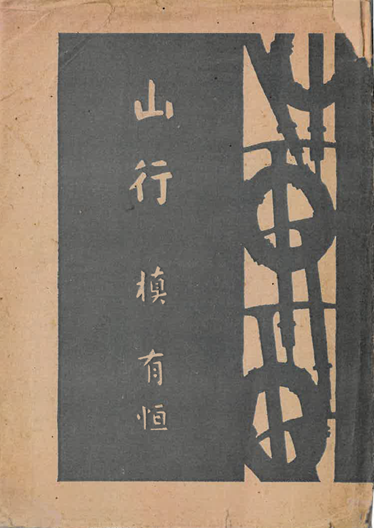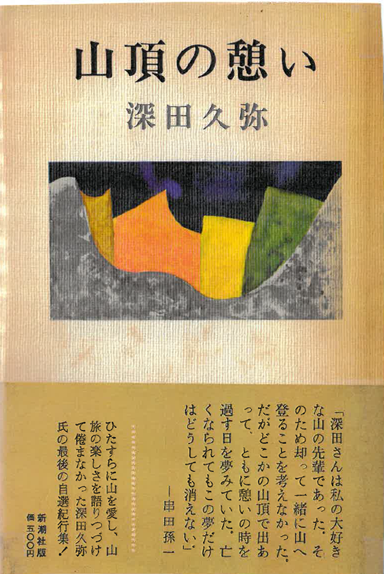2022年6月24日(金)15:00~16:00、東京都練馬区のNPO-AIUE本部で第20回総会を開催する。会員197人、委任状29人、web出席者:北海道・東北3人(須藤、渡辺、小柳)、関東1人(前川)、関西3人(森山・藤本・山田)、九州4人(依田・福田・高・バート)、対面出席8人(吉田・中嶋・高口・市川・佐土原・渋田・小林・尾島)で盛況。小林事務局長の進行で、吉田理事長は手際よく司会。決議案、支部報告後に横浜での第19回国際シンポは、佐土原・村上・高口の実行委員会で順調に進むとの報告。論文の応募状況について高君より報告。中国・韓国他、海外の状況以上に日本国内での支援と同時に、コロナ禍での出国や帰国後が心配。
最後に、私から4点お願いする。
①2018年、理事長を吉田君に交代したが、NPO-AIUEや国際会議の継続を考え、会長職を創設。経営基盤を確実にするため、DHC協会等、私の関係する各種法人との連携を強化する。
②2020年度に拠点を銀座から練馬に移したこともあって、NPOの研究資金が不足。最小限、年間300万円程確保するためには、事業部と担当を設けたい。
イ.BΣS事業(増田(幸)・渋田) ロ.JCM事業(吉田・前川) ハ.DHC事業(佐土原・村上) ニ.安全研継承(高口・秋山) ホ.PRH再生(原・中島) ヘ.国際投資(市川・州一) ト.出版・図書等(久保田・岡)を考えている。
③NPO-AIUEとは別に、初心通り、九州に一般社団法人(仮)国際都市環境学会を設立。依田・福田・高・バートを中心に、2023年度には設立。
④2024年10月頃に、尾島の出版(「都市環境学へ」と「尾島研究室の軌跡」の各続編)を予定。2冊の配布と記念会に10~20人の実行委員会(代表:中嶋君)を予定したい。これ迄の尾島研出版物は100種、約3000~5000冊の在庫あり。その処分はNPOに期待している。
以上4点をお願いして、自由討論に入る。
Web11人と対面8人での自由討論は画像を活用したことにより、実にドラマチックに展開した。九州の福田・依田・高・バート君の決意や東北の渡邉新学長はなかなかに立派で頼もしく見えたのも、渋田君の演出の成果であった。また高口君のNPOと一般社団法人の名称を変える提案は、「アジア」と「国際」を冠する二つの都市環境学会で了解する。
以上で総会終了。
Web参加者には申し訳なかったが、16:30~18:00は懇親会。練馬での久しぶり多勢の宴席になった。Blog58で調達した富山の銘酒「黒部峡」の吟醸と大吟醸酒を飲み比べる。お弁当は米八のおこわ弁当、デザートは吉田君の持参した市川ちもと「手児奈の里」で、銀座オフィスとは違ったアットホームな雰囲気で、これからのNPOや一般社団法人としての日本・アジア・世界の都市環境論に花が咲く。
2000年、北九州で理工総研を設立し、選択定年後の活動基盤としてアジア都市環境学会を創立。2003年のNPO化から20年。国際会議は横浜大会で19回で、次の韓国大会が20周年である。
九州を拠点とする都市環境学会はアジアから世界へと本格的なAIUE:Association of International Urban Environment(一社)A.I.U.E.として発展するときが来たのだ。温泉でのDrink & Togetherを目的に、早稲田の一研究室卒業生達の懇親会的場を脱皮して、国際的に都市環境学の発展に寄与する時が来たと実感したのは、2021年に北九州市立大学訪問時であった。彼らが間もなく定年退職したときには、その実績を普及させる場が必要になる。大学から学会へと職場を移しての30年間があること。アジアのみならず、世界中が都市環境学の必要性を求めているとき、福田・高・バート君を中心に、依田・堀・三浦君等が協力すれば、新しい職場が創造できる。
まずは最小限(会員年会費1万円、賛助法人会費1口3万円/年)の一般社団法人国際都市環境学会がその職場であり、そのためにこその設立である。それをNPO-AIUEが全面支援することで、その第1回(通算第21回目)を2024年の西安シンポにして欲しいと願う次第である。
これを機会に、NPO-AIUEのホームページに新組織と改正定款(案)を記載する予定であり、また私の日記的Blogを公表しているので、御意見を戴ければ幸いである。また本日のBlogでの実名表記と敬称を略した失礼は高齢に免じてお許しを。
(コメントを受けて一部修正しました)