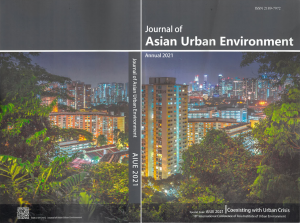2022年2月23日は天皇誕生日の休日とあって、コロナ禍であったが、息子に西武デパートで古書市最終日だからと誘われて出かけた。大学定年後は、月一回必ず、丸善や紀伊國屋書店で1~2時間、面白い本をあさっていたが、最近、何故か面倒になってきていたのに、古書市と聞いて急に興味が湧いたのだ。
約束の40分間で買い求めた10冊の中で、特に気に入って、その晩に完読したのが冠松次郎の「わが山・わが渓」(昭和17年、墨水書房)と再版「峰と渓」(2002年、河出書房新書)である。

1949年、12歳の時に初めて体験した3泊4日の立山登山がやみつきになって、中学・高校時代には家の奥庭で遊ぶ気楽な気持ちで、立山・白馬・黒部等、近郊の山や渓のみならず、富士山から中央アルプスまで山仲間と遠征する間に、山小屋やテントの中でガイドや友人達から聞いた山々の伝説で最も忘れられない人の名は冠松次郎(1883-1970)であった。
何故なら、剱沢から黒部へ下山する度に何度も挑戦しようとして出来ず、冠松次郎だけが、私の生まれた昭和12年に見たという黒部の「幻の大滝」伝説である。当時、冠松次郎は地元のガイド(ボッカ、剱の初登頂行者の類)の一人ぐらいに考えていたため、有名なアルピニストで著書もある人とは考えてもいなかった。この時代から既に70年、最近になってテレビでドローンで空中撮影した「幻の大滝」と、更に近くまでカメラマンや登山家が大変な渓谷を登って近づく場面等が放送されて、やっと本当に「幻の大滝」が存在したことや、幻ではなく実在する秘境の名瀑であったことを知ったが、まさかこの古書市で冠松次郎の古書を2冊も手に出来たのは軌跡に思えた。
この著書の一節、昭和12年6月記「大勢の力で幻の大滝に近づくも九死に一生を得ての撤退。」
昭和12年7月記「滝を語る」で「剱岳三千余米突に源を発する剱沢中央部の瀑布・剱の大瀑である。その滝の全貌は今日、未だ吾人の前に展開されていない。」
昭和13年6月記「剱の大滝の上まで深雪の上をのみ行く今は二時間で楽に着くことが出来た。大雪渓はそこで大きく切れている。そして剱の大滝の頭が雪の底から溢れるように奔出している。私等は数丈の雪崖にステップを切ってそのすぐ上まで降りて見た。脚下は井戸側のように丸く削られた花崗岩の大岩壁だ。その底の方から水煙が雲のように濛々と立ち勝って、剱沢全流の水は棒立ちになって崩落している。下を覗くとまるで底なし井戸だ。私等は瀑布を囲む数百米突の断崖をカメラに収めると来た道をまた上流に引き返した。」
黒部の秘境・剱沢の「幻の大滝」を一度は見たいと考えていた10代の夢が、80代になってドローンの映像を見て、幻の行者の如き山男・冠松次郎が著名なアルピニストで、その著作で上記の如く、生々しく「幻の大滝」に近づき、一見するために何度も何度も、しかも一人でなく、時には大勢の力を借りて挑戦していたことを今になって知った。

この興奮から、このBlogを書きながらもう一冊、建築家槇文彦の叔父・槙有恒(1894-1988)の古書「山行」(昭和23年7月、岡書店)を一読して驚く。なんとこの本に「板倉勝宣君の死(大正12年1月)」の章があった。
富山高校時代の友達には立山山麓から通学している学生が多く、その一人に雄山神社の宮司の息子(遠北邦彦君)がいて、彼を中心に多くの山小屋に仲間がいたことが幸いして、全国・四季の山々を楽しめた。
早稲田の建築学科に入ると時間がなく、東京からの山歩きは大変で、土日や春夏の休みくらいになったが、学部・大学院時代の9年間は立山・黒部開山・中興の祖である佐伯宗義代議士別宅での寄宿生活もあって、アルバイトを兼ねての立山山麓を散策する機会が多かった。
印象に残っているのは、小学校から中学校時代にはまだ称名滝を登って弥陀ヶ原から天狗平・室堂ルートか立山温泉経由、松尾峠かザラ峠ルートで一ノ越ルートが主で、何度もこの道を歩く度に、著名な登山家である槙有恒一行が何故こんなところで遭難したのかを知りたいと思っていた。
特に大学院2年の5月連休時、立山登頂後に一ノ越で骨折。一本足スキーで天狗平から松尾峠を目指して滑降しつつ、弥陀ヶ原を見ながら、何度も疲れて果てて天を仰いで休みながら、槙有恒の遭難時伝説を想い出して頑張り、下山したこともあり、天候次第でこの辺が一番危険で、一番美しく快適な所と認識していた。しかしこの本のこの章を読むまで、実際の遭難状況を知らぬままに居たことである。
この生々しい体験記を読みながら、若い頃に何度もこの遭難記に類似した体験をしたことを想い出し、改めて私が山に行く度、下山するまで母がどれほど心配していたかよくわかった。仏壇の母に感謝し、今更、山歩きの危険さを知るのであった。
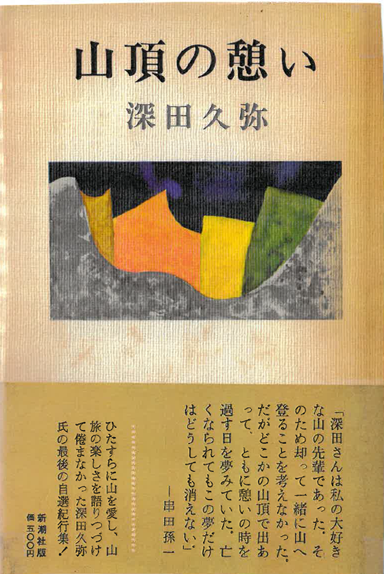
ついでにもう一冊、深田久弥著「山頂の想い」(昭和46年7月、新潮社)のあとがきに、妻・深田志げ子は「この本は図らずも自選の最後の山の紀行文集となった」とあり、最初に久弥は「日本百名山その後」として「百の名山は私個人の選択であって、客観的妥当性があるわけでないが、しかし一つの目安にはなると見えて、百のうち自分は幾つ登ったか目次にしるしをつけて、その数のふえて行くのを楽しみにしている読者が多いようである。」また「この本は案外評判がよく、1964年の初版以来、毎年増刷を重ね、今年12刷に及んだ。」
私自身、この本の初版以来3~4冊は購入し、60座以上に〇印を付している。特に大学院生から一人で山を歩くことが多くなって、いつかこの百名山の簡にして要を得た山案内記は、5万分1地図同様、必携の書になっていた。最近では200名山から300~500名山と誰が編集しているかわからなくなっていたが、そのこともすでに深田久弥(1903-1971)は見越して居たことを教えられた。
10冊購入の内4冊は山の本であったが、他にも面白い古書が手元にあって、これからは古書の旅に出るのも健康の秘訣と想った次第である。