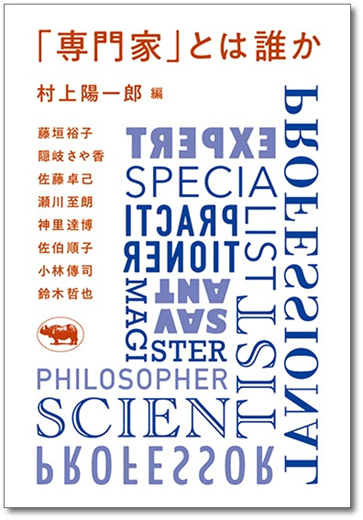
Blog50(2022年2月)で、「村上陽一郎著『エリートと教養』は本当のエリートだからこそ書ける教養書」と評したが、今度の村上陽一郎編『「専門家」とは誰か』も又、本当の専門家だからこそ編集できた「専門家論」である。失礼を承知で、刺激され、共鳴した各先生の文章に傍線を引いた9章を以下に記した。関心を持たれた方は本文を読んでください。
○はじめに
村上先生は「専門家と言われる人のその分野における知識は、恐るべき深さである一方で、他の領域への知識の万能性は、全く期待できない、という事態も深刻である。」
○専門家とは何か
村上先生は「『専門』は、『科目』という用語を借りた『専科』という意味が前面に現れた使い方が多く、実際に『専科』という言葉も用いられる。
英語の<expert>は『専』に偏した意味合いである。この反対語として<amateur>(素人)が挙げられる。
19世紀半ばのヨーロッパで顕著になり始めた『専門化』現象に、それをそっくり取り込んだのが、近代化の出発点にあった日本であった。西欧から輸入する学問(sciences)を『科に岐れた学問』として捉えた結果が、『科学』という和製造語になって、今日まで日本社会の根幹に座った。
現在では物理学者という専門家はもはや存在しない。ある領域で真の専門家と呼び得る人の数は、世界中でも50人を越えるかどうか。」
○隣の領域に口出しするということ-専門家のためのリベラルアーツ
東京大学教養学部の藤垣裕子教授は「日本で何故あのような原発事故を起こしてしまったのか。原子力研究も地震や津波研究でも世界トップクラスの研究をしていたのに。
東京大学教養学部の藤垣裕子教授は「日本で何故あのような原発事故を起こしてしまったのか。原子力研究も地震や津波研究でも世界トップクラスの研究をしていたのに。
専門化が進んで、隣の領域に口出しできる習慣がなかった点が示唆された。
多様な知を結集するのは、異なる領域間の往復が必要となる。往復の技術を培うために専門家のためのリベラルアーツがある。」
○科学と「専門家」を巡る諸概念の歴史
東京大学教育学研究科の隠岐さや香教授は「有識者会議に呼ばれている状態のその人がexpertなのである。社会が平等になるほどに、あらゆる職業がprofessionと呼ばれ、誰もが何かのexpertのように振る舞う機会が増えている。」
○「ネガティブ・リテラシー」の時代へ
京都大学教育学研究科の佐藤卓己教授は「専門家になるということは、われわれが発見する要素の数を増やすことであり、それに加えて、常識を無視する習慣をつけることである。」
「何かの専門家になるということは、別の何かの専門家ではないということである。」
○ジャーナリストと専門家は協働できるか
早稲田大学政治経済学術院の瀬川至朗教授は、「社会における本当の専門家」の要件は、
・専門知を有し、その知識を日々更新している
・自らの専門知について批判的
・哲学的に検討し、意義と限界を理解している
・専門知に基づいて社会やメディアに向けて語る意志がある
・メディアの特性を理解し、適切に活用できる
○リスク時代における行政と専門家-英国BSE問題から
千葉大学国際学術研究院の神里達博教授は「専門家の助言なしに行政を遂行することは不可能である。与えられた課題にふさわしい専門家を探すのは案外難しい。若手研究者は本業で手一杯であることが多く、その点でも比較的高齢の『大御所』が選ばれやすい。審議会で専門知を生かすには、先ずは幅広い知見に基づく検討の上で、専門知を審議会に求める二段階方式を提言する。」
○女子教育と男子教育からみる「教養」と「専門」
同志社大学社会学研究科の佐伯順子教授は「『教養』ある『社会』人、良質な『教養』を身につけた『専門』家を養成することは、短期的成果はみえにくいとしても、長い目で見て環境破壊や国際紛争において的確な判断を下すことができる真の国際的知見を備えた社会的リーダーの出現にもつながる。」
○社会と科学をつなぐ新しい「専門家」
大阪大学の小林傳司名誉教授は「専門家の二種の類型として、一つは自らの専門的知識や技能が不断に非専門家との接触を通して利用される現場に立ち会う専門家である。『臨床の専門家』と呼ぼう。
もう一つは自らの専門的知識や技能の流通や使用が比較的閉じた同業者集団に限られ、その種の知識の利用が非専門に及ぶ場面と相対的に切り離された専門家である。いわゆる『基礎研究の専門家』である。同一の人間が両方の役割を演じることが多いのが普通である。しかし現代社会には『社会における科学と社会のための科学』として「プロデューサー」的「媒介の専門家」として哲学者が必要。」
○運動としての専門知-対話型専門知と2061年の子どもたちのために
京都大学学術出版会の鈴木哲也専務理事は「『専門家』と社会の関係は、今日、危機と言っても良い状況に至った。社会の中で専門家が専門家としての見識を示すことの正統性/正当性を毀損する動きが、次々と起こった。COVID-19においては、日本での感染拡大が懸念されるようになった当初、政府は大慌てで専門家に意見を諮ったが、外出自粛や飲食業の休業など厳しい行動規制が提起されるや、中には専門家を公然と毀損するような発言も含めその意見を軽視・無視する傾向はすぐに現れ」「専門外を知り、専門外と対話する力『威信』。狭い専門の中での威信が必然的に生起するサイロ(タコツボ)化が、社会経済に大打撃を与えたことさえある。」
実は、この本にやたら傍線を引いたのは、人生の家庭教師であった魚津に住む早稲田の先輩・浜多弘之氏の通夜と葬儀のため、東京から富山への新幹線往復と通夜の夜、断続的に読んだためである。大学の進学相談から今日に至る70年もの長い間、郷里の富山での建築やまちづくりの仕事で面倒をみて貰っていた兄貴分の逝去は突然であった。
人生百年時代と思い込んで、これから愈々本格的に郷里の家やまちづくり再生の相談をする予定であったから、Blog72(10月9日)に「万事休す」と書いた程の衝撃であった。故浜多弘之氏の弔辞を依頼されたこともあり、本書とともに、2020年2月、文春新書『死ねない時代の哲学』と2022年2月の中公新書ラクレ『エリートと教養』を鞄に入れた帰省であった。

自分も既に85歳を越えていながら、90歳で逝去した先輩の死が突然と考え、「万事休す」などとブログに書く様では。考えるまでもなく、私には哲学も教養もないことの証である。
「臨床の専門家」として、又、国が認める職能独占の一級建築士というprofessionをもってこれまで生計を立て、大学院では都市の建築をつくるためにと都市環境工学専修を新設して「基礎研究の専門家」となった。そのためか多くの審議会や国際会議に出席し、日本学術会議の会員にもなった。しかしこの段になって、改めて専門家には教養や哲学のベースが必要不可欠であることを教えられた上に、簡単には「死ねないこと」も教えられ、本当に「万事休している。」
